今回は歴史上でも珍しいと思われる女性の君主を何人かピックアップして、ご紹介していこうと思います。何かの参考になったら幸いです。
- マティルダ『無政府時代の女性君主』
- アリエノール『時代の中心人物だったアキテーヌ公領の君主』
- イサベル1世『スペインの礎を築いた女王』
- フアナ『狂女と化した女王』
- エリザベス1世『国と婚姻した処女王』
- ジェーン・グレイ『九日間の女王』
- メアリー1世『血まみれの女王』
- メアリー・スチュワート『処刑されたスコットランド女王』
- マリア・テレジア『ハプスブルク家出身の女帝』
- ヴィクトリア女王『大英帝国の最盛期を築いた女王』
- クレオパトラ『古代エジプト最後の女王』
- ゼノビア『血の気の多い戦士女王』
- クリスティーナ『王位を捨て旅に出た女王』
- エカチェリーナ二世『玉座の娼婦』
- ハトシェプスト『公式の記録から抹消された王』
- 武則天『中国史上唯一の女帝』
- 孝謙天皇『男に惑わされた女帝』
- タマラ『軍事的な才能に目覚めた女王』
- リブサ『女性優位の国家を築いた女王』
- ヤドヴィカ『聖人に数えられた王』
- ンジンガ『奴隷貿易と戦ったアフリカの女王』
- ラナヴァロナ1世『近代化を阻止したマダカスカルの女王』
マティルダ『無政府時代の女性君主』

(1102年〜1167年)
イングランド史上初の女性君主はエリザベス1世のイメージもあるかもしれないが、実はマティルダが一番最初だったりする。
父のヘンリー1世が亡くなると従兄弟であるスティーブンが王位を継承した。それに不服を唱えたのがマティルダだ。スティーブンは生前のヘンリー1世と王位を継承しないことを約束していたが、ローマ教皇との友好な関係を築くなどして根回しをしていたので、なんの問題もなく王位を継承することができた。しかし、スティーブンは諸侯や教会に多く譲渡していたので、国をまとめる力がなかったのだ。
好機と見たマティルダはイングランドに上陸して王位奪還を求めた。こうして内乱に突入したイングランドは「無政府時代」となり国力を大幅に失うことになる。
最後にはスティーブンの生涯に渡る王位を認め、継承者にマティルダがなることが決定した。女王として戴冠することはなかったので正式な女王ではない。また内乱によってイングランドが荒れたことでマティルダの評価あんまり高くはない。
アリエノール『時代の中心人物だったアキテーヌ公領の君主』

(1122〜1204)
フランス王妃だったこともあれば、イングランド王妃も戴冠した経緯を持つアキテーヌ領の君主。息子にリチャード1世がいるなど、子孫の多くが君主や王妃になったことから「ヨーロッパの祖母」と呼ばれた。
アリエノールが生まれたアキテーヌ公領はフランスの3分の1を領土にしていた。アリエノールも名門の女性として、高等な教育を受けた。
父のギヨームが亡くなると、アキテーヌ公領を狙ってフランス王が、自身の息子とアリエノールを結婚させた。この政略結婚は上手くいかずに破局することになると、無政府状態で荒れていたイングランドの継承者であるヘンリー二世を支持して再婚した。
イングランドはアキテーヌと合併したことで大国になり、フランスにとって脅威となるが、アリエノールはアキテーヌ領を維持することにしか関心がなかったので、ヘンリー二世と対立する事になる。
ついには、息子たちを唆してヘンリー二世と対立する構図を作り上げた。だが、アリエノールはヘンリー二世によって、長い監禁生活を送ることになる。アリエノールが最も溺愛し、アキテーヌ領の継承者に指名したリチャード1世は、父、兄弟との戦いに勝利して自身がイングランドの王位を手に入れた。リチャード1世によって解放されたアリエノールは摂政としてリチャードを支えた。
イサベル1世『スペインの礎を築いた女王』

(1451〜1504)
夫のフェルナンド二世と「カトリック両王」と言われたカスティーリャの女王で、彼女の死後に夫の領土と完全な結合して「スペイン王国」が誕生した。
国王の娘として生まれたが、父が崩御して異母兄エンリケ王が即位すると、母と弟と共に不遇な生活を送ることになる。エンリケ王の人気が低下すると、弟のアルフォンソが即位する話が進むなど、かなり複雑なことになった。
アルフォンソが急死したことで、イサベルはポルトガルに嫁ぐ話が舞い込む。事前に察知していたイサベルは、地中海に覇権を握っていたアラゴン王国のフェルナンドと勝手に結婚した。
エンリケの死、王位継承問題の乗り越えたイサベルは夫と共に即位して「スペイン王国」が誕生させる。イスラム国家との戦争に勝利して800年に渡るレコンキスタを完結させると、「カトリック両王」の称号を得ることになる。また、コロンブスを支援したことでも有名で、スペイン黄金時代の礎を築いた。
フアナ『狂女と化した女王』

(1479〜1555)
カスティーリャの女王で、上記でご紹介したイサベル1世の娘。精神に異常を来して約40年間も幽閉されたことで有名な女王である。
幼少の頃から内気で読書ばかりしているような子供だったそうだ。多数の言語を習得したが、一人でいることを好み、政治に関心を持つことがなかった。おそらく内気な性格で刺激に弱い性格だったと思われる。フアナの精神が狂い始めたのが結婚後であったことからも想像するに相当なストレスだったようだ。
フアナは神聖ローマ皇帝の息子であるフィリップと結婚する。このフィリップとは当初は仲が良かったが、フィリップはフアナの前で他の女性と仲良くするなど、二人の仲は険悪になっていった。
ついにはフアナの精神は異常であるから王位を譲れと、カトリック両王に訴えると故郷に帰ってしまったのだ。これにフアナは異常なほどのショックを受けることになる。
イサベル一世が崩御するとフィリップはかつての愛を取り戻したとフアナに近づき王位継承権を手に入れようと模索するが、フアナは頑なに拒否した。
フィリップはあらゆる手を尽くして王位を狙うが、急死してしまう。フアナのストレスは自身の要領を超えて、夫の埋葬を許さずに棺を馬車に乗せて国内を数年間も渡り歩いた。その後40年間も幽閉生活を強いられて、政治の世界からも忘れ去られた。
エリザベス1世『国と婚姻した処女王』

(1533〜1603)
生涯を独身で過ごし「国と結婚した」自ら豪語したことからも「処女王」と呼ばれるイングランドの女王。イングランド王のヘンリー8世の娘として生まれたが、母が処刑されたことで、庶子として地位が下がってしまう。それでもヘンリーからの愛を変わらなかったので順位は低いが王位継承権はあった。
エリザベスは生涯を独身で過ごして「処女王」と呼ばれていたが、何も男性関係がなかったわけではない。若い頃のエリザベスは義母の夫と不倫関係にあった。この男は王を追放する計画に加担していたので処刑されてしまい、エリザベスは尋問を受ける羽目になってしまう。その後「ブラッティ・メアリー」や「メアリー・スチュワート」と王位継承を巡り、最終的には自身がイングランド王に即位した。
当時、最強と謳われたスペインのアルマダ艦隊を破りイングランドが強国であると知らしめた。
ジェーン・グレイ『九日間の女王』

(1537〜1554)
マティルダよりも、エリザベス1世よりも先にイングランド女王を戴冠した伝説の女王が、ジェーン・グレイである。しかし、ジェーンは僅か九日間の在位で処刑されることになってしまった。
エドワード6世が幼く、病弱であり、次の継承者はメアリーになることは確定的だった。しかしながら、摂政のダドリーはメアリーの即位を拒みジェーンを即位させようと暗躍を始める。ジェーンを女王に据えて、自身の子供と結婚させようとしたのだ。
エドワード6世は、メアリーをよく思っていなかったことを利用して、次期国王にジェーンを指名する遺言を書かせることに成功する。エドワードが病死すると、ジェーンが即位することになるが、そう上手くはいかなかった。
聡明であったジェーンは自身に正当な継承権はないと即位を拒んだのだ。それだけではなくメアリーは不当であると訴えて、クーデターを起こした。ジェーンは逮捕されて、僅か九日間の王位の果てに、大反逆者として処刑されることになる。ジェーンは政治の道具として利用されて、悲劇的な結末を迎えてしまった。
メアリー1世『血まみれの女王』

(1516〜1558)
ヘンリー8世の最初の嫁との娘であり、エリザベス1世の姉に当たる。プロテスタントを迫害して、虐殺を行ったことから「ブラッディ・メアリー」と呼ばれている。
メアリーは幼少から美しいことで評判が良く、ヘンリー8世はかなり早い段階(2歳とか)で名家の男子との縁談の話を進めていた。だが、男子を望んでいたヘンリー8世はメアリーの母との婚姻を解消することを決断する。これよってメアリーは王女の身分を剥奪されて庶子に格下げされた。
両親の婚姻の解消を絶対認めなかったメアリーはヘンリー8世と対立することになる。やがて、ヘンリー8世と最後に婚姻を結んだ嫁が家族を大切にするように説得すると、メアリーとエリザベスは王位継承権を得ることになった。
そして、ジェーン・グレイから王位を奪い自身がイングランド王となった。宗教改革に逆行してカトリックに強引に戻したことから「ブラッディ・メアリー」と呼ばれることになる。その後、スペインのフェリペ2世と結婚したが、病気によってメアリーは後継ぎを生まずに亡くなることになる。スペインとの結婚はいいことがなく、エリザベスの時代になると、スペインと王位を巡ることになった。
メアリー・スチュワート『処刑されたスコットランド女王』

(1542〜1587)
生後六日でスコットランドの女王に即位したメアリーは、成長してフランス王と結婚してフランス王妃にもなった。エリザベス1世がイングランドの王位を継承すると、「エリザベスは庶子であり、メアリーこそが正当後継者である」と抗議したことでエリザベスとメアリーは対立するようになる。
フランス王となった夫が亡くなると、後継を産めなかったメアリーはスコットランドに帰還することになる。メアリーは再婚することになるが、その相手はイングランドで権力のある人物であり、メアリーは彼に権力を与えた。
しかし、彼は権力に溺れる人物でメアリーは彼を見切ってしまい、別の人物を愛するようになる。そんなかで、夫が亡くなりメアリー再び再婚した。
これが大問題となる。カトリックでは離婚は許されることではなかったので、メアリーが殺害を加担して結婚したのではと国内外から非難された。
25歳だったメアリーはクーデターを起こされたことで、廃位することになりイングランドに亡命した。エリザベスは正統な王位継承権を持つメアリーを危険視しながらも、19年間もほぼ自由な幽閉生活を送らせました。しかし、メアリーがたびたびイングランドの王位を主張したこともあり、44歳で処刑された。
マリア・テレジア『ハプスブルク家出身の女帝』

(1717〜1780)
オーストリア、ハンガリー、ボヘミアの君主で、即位には批判の声があったが、立派に女帝をやり遂げた。マリー・アントワネットをはじめ子宝に恵まれたことで有名で「ヨーロッパの祖母」と評価される。
神聖ローマ皇帝カール6世の子供として生まれた。男子に恵まれなかったカールはマリアが男子を生むことを願ったと言う。カール6世は亡くなる前に、マリアが君主になることを認めるように各国の代表に願ったが、上手くはいかなかった。
マリアが君主になると各国はオーストリアの領土を奪うべく動き出したのだ。これをオーストリア継承戦争と言う。各国の代表はマリアが本来王位を継ぐための教育を受けてないので、無知で領土を奪うの容易であると評価した。
しかし、君主としての才能を発揮したマリアは領土を守護することに成功したのだ。これには時代を代表する英雄であるプロイセンのフリードリヒ大王も後年になってマリアを認めざるを得なかった。
ヴィクトリア女王『大英帝国の最盛期を築いた女王』

(1819〜1901)
世界の産業革命を席巻した時代の女王で、世界の陸地の四分の1を支配してイングランドの最盛期を築いた。
18歳で即位して、63年以上も女王の座についていたが、両親はザクセンの出身で英語よりもドイツ語を扱っていたと言う。夫となったアルバートもドイツ系の出身者だったので、王位を継承した時も反対の声があったようだ。
それが原因もあり、ヴィクトリア女王はロンドンで過ごすことを好まず孤立した生活を望んだ。孤立した生活はアルバートとヴィクトリア夫婦の仲を深くする要因になり9人の子供に恵まれた。
また、アルバートは政治家としても有能だったようで、女王ヴィクトリアに強い刺激を与えて、イングランドでの権威も強固にしていったが、42歳で亡くなった。
夫の死のショックでヴィクトリアは10年間も公務を行わなかった。立ち直ったヴィクトリアは、大英帝国の最盛期を築き、インドの女帝を名乗るまでに至った。
ヴィクトリアは、アリエノールやマリア・テレジアと同様に子孫が各国の王族に嫁いだことから「ヨーロッパの祖母」と呼ばれるが、彼女の死後に第一次世界大戦が勃発したことで、子孫達は対立することになってしまった。
クレオパトラ『古代エジプト最後の女王』
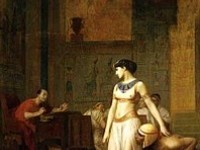
(前69〜前30)
絶世の美女で有名な古代エジプトの女王。世界三大美女として有名であるが、最も優れた部分は容姿ではなく、楽器のような美しい声と、7つの言語を操る聡明さであった。
弟と共同で即位するが、意見が合わず対立することになってしまい、エジプトを追い出されることになる。
そこで、クレオパトラは遠征に来ていたローマのカエサルに取り入りエジプトを奪還した。エジプトの女王としての地位を取り戻し、カエサルの愛人となり子供を産んだクレオパトラは最盛期を迎えた。
カエサルが暗殺されると、今度はアントニウスに取り入った。クレオパトラとアントニウスはローマと全面戦争をして敗北する。クレオパトラは毒蛇に自身を噛ませて自決する選択をした。ちなみに夜の技の達人だったようです。
ゼノビア『血の気の多い戦士女王』

(約230〜不明)
オリエント世界最強の女傑と謳われるパルミラの女王。ゼノビアは出生どころか生涯に関して不明な点が多い。正式に歴史の表舞台に登場するのは二度目の結婚の時だ。
パルミラを治める男と結婚したのだが、王位継承権を持つものが次々と殺害されたことでゼノビアが王位を継承することになる。
そして、ゼノビアはローマからの独立を狙ってクーデターを起こしたのであった。
パルミラはローマに服従する弱小国に過ぎなかったが、ローマが混乱している隙を狙って兵を動かしたのだ。ゼノビアは自らが軍服を着込み戦ったことから「戦士女王」と言われた。
ローマに歯向かう逆賊を討つと言う名目でエジプトを攻略すると、あっという間に巨大大国を築き、自身をクレオパトラの後継者を名乗った。しかし、本気を出したローマによってゼノビアは敗北してしまい、王国は瓦解した。ゼノビアはローマに送還されて、見せ物にされた。
クリスティーナ『王位を捨て旅に出た女王』

(1626〜1689)
僅か6歳で即位したスウェーデンの女王。父は北方の獅子王グスタフ・アドルフで、誕生した時は男子に間違えられて国中に誤報が流れた。
女の子であることが判明すると母は落胆したが、父は「我々を騙したのだから将来有望である」と彼女を早々に後継者に指名して高等教育を受けることになった。
古典や帝王学、剣に乗馬など、男児のように育てられたクリスティーナは、父の死により6歳で即位した。天才的な才能を秘めた女性であったが、政治には無関心だったようで二十歳になると王位を譲り、各国を見て回る旅に出た。
数十年後には王位を譲った人物が亡くなったので、自身の王位を主張して再び王位に返り咲こうとするが上手くはいかなった。62歳で亡くなる。
エカチェリーナ二世『玉座の娼婦』

(1729〜1796)
夫にクーデターを起こして自身が王位を勝ち取ったロシアの女帝。ロシアの女帝であるが、出身がドイツの生まれだったりする。
本来なら皇太子の妃になれる身分ではなく、美貌にも恵まれなかった。しかし、幼少期から努力を積み重ねて、高い教養を身に付けつつ美貌にも磨きをかけた。
運良く、ロシアの皇太子ピョートル3世の妃の候補になることができた。夫とは不仲であったと言う。と言うかピョートルは発達障害の疑いがある人物で、エカチェリーナと性交渉をすることを拒んでいたし、ドイツが好きだったらしく、ロシア兵にドイツ兵の格好をさせたりと、評判は良くなかった。
しまいには戦争の勝利を目前にして、相手が憧れの人物であったプロイセンのフリードリヒ大王だからと兵を撤退させれしまったのだ。
対してエカチェリーナはロシアの人達に認めてもらえるように、ロシア語を短時間で取得して、ロシア正教に改宗するなど着実に評判を上げていった。
ついにはクーデターを起こして夫を追い出したのだ。エカチェリーナは30年近くロシアの君主を務めたが、その裏で数百人の愛人を抱えてたことから孫のニコライから「玉座の上の娼婦」と蔑称された。
ハトシェプスト『公式の記録から抹消された王』
(在位・紀元前1479〜紀元前1458)
古代エジプトのファラオであるトトメス2世は幼い子供を残して亡くなってしまう。トトメス2世の遺言で息子のトトメス3世が即位することになるが、トトメス3世はまだ幼いので母であるハトシェプストと共同で即位することになった。
古代エジプトでは女性がファラオになることを慣例的によろしくはないので、ハトシェプストは付け髭などの男装をしたそうだ。息子が成長してもハトシェプストは王位の継続を続けて、実質的に最大権力の誇示を続けた。
彼女の死後に息子のトトメス3世は女性が君主として君臨した記録を全て消去した。これは息子と母の仲が悪かったのではなく慣例に従ったからに過ぎない。現にハトシェプストは生前に計画した建造物を息子のトトメス3世が引き継いで完成させている。
武則天『中国史上唯一の女帝』

(624〜705)
病弱な夫に代わって国を回した中国史上唯一の女帝であるが、中国三代悪女に数えられる女性でもある。14歳で皇帝の愛人となった武則天であったが、高齢だった皇帝が亡くなり後宮を去ることになるも、美貌によって次期皇帝の愛人となった。
武則天は皇后の座を狙うようになり、自身の子供を殺害してあたかも皇后によって殺された状況を作り上げたのだ。罪を問われた皇后に代わって武則天が皇后になった。
皇帝の妻になった武則天は、皇帝が年下で病弱であり優柔不断を良いことに事実上皇帝以上の発言力を持つようになった。絶対的な権力を欲するようになった武則天は、後継ぎである長男を毒殺、次男は気に入らないと王位を三男に譲らせた。その三男も幽閉生活を強いて、やはり自身が国のトップなり皇帝を名乗るようになった。
孝謙天皇『男に惑わされた女帝』

(718〜770)
日本史上6番目の女性天皇で、孝謙天皇以降850年は女性が天皇になることはなかった。聖武天皇と光明皇后の間に生まれた孝謙天皇は女性で初めて皇太子となり、病気がちな父に変わって天皇に即位することになる。
その孝謙天皇も病気によって身体は蝕まれていたが、藤原仲麻呂と言う優秀な人材に恵まれた孝謙天皇はクーデターを阻止するなど、なんとか統治を続けた。
孝謙天皇にある出会いがあった。僧の道鏡に看病してもらったことをきっかけに彼を寵愛するようになり、恋仲になったのだ。出世欲の強い藤原仲麻呂は、焦心からクーデターを起こしてしまい殺害される。
ライバルがいなくなった道鏡は自身の権力を強めていき、ついには天皇の地位まで狙うようになってしまう。とある貴族に天皇に推薦されたと嘘をついたのだ。この嘘は簡単にバレて道鏡は左遷された。
タマラ『軍事的な才能に目覚めた女王』

(1160〜1213)
中世グルジア王国の最盛期を築いた女王。後継者がいなかったので18歳の時に父と共同で即位することになったタマラは、母性的な君主として国民から慕われた。
貴族からの反対の声もあったが女性に高い地位を与えて認めていることは、周囲のイスラム国と差別化を図ることに繋がったと言う。タマラは周囲のイスラム国との戦う必要があった。
そこでキエフ(ロシア)からイスラムとの戦いで活躍していた軍人を夫として招き入れて、軍事司令官として活躍することを期待した。しかし、この男とは性格が合わず多額の財産を与えて離縁することになる。
タマラが自らが軍を率いることになると、軍事的な才能を開花していき、グルジア王国は最盛期を迎えた。
その強さから叙情詩「豹皮の騎士」がタマラに捧げられるなど、伝説となる。物語となったタマラは時を越えてシェイクスピアなどに凶悪な女戦士として描かれることになるが、元夫が軍を率いて幾度も進軍してきても、元夫の命を奪うことはしないなど寛容であった。
リブサ『女性優位の国家を築いた女王』
(約680〜約738)
リブサはチェコ西部ボヘミア地方に実在した女王の名前である。二十歳で即位したリブサは、二人の姉妹に軍事と政治の補佐をしてもらいながら統治をした。リブサは女性に軍事的な教育を施して、女性のみが高位の地位を与える統治を行った。
もちろん男性によるクーデターが起こったが、鎮圧している。女性のみの軍隊で領土を拡大していったが、リブサは女将軍であったヴァラスカによる反乱「ボヘミア乙女戦争」の果てに敗北した。
ヴァラスカは全ての公職を女性に就かせて、女性に軍事的な奉仕を課した。男性に関して全ての指を切断して、目をえぐり無力にしたと言う。ヴィドヴォレ山中には「処女の街」と呼ばれる遺跡があるが、ここがヴァラスカの本拠地だったとされる。
ヤドヴィカ『聖人に数えられた王』

(1374〜1399)
ヤドヴィカはポーランドの王で、ヨーロッパでも珍しく「女王」ではなく「王」として即位した。ポーランドの宮殿にはヨーロッパ各地の芸術家や学者が集まっていた。
その環境で育ったヤドヴィカは複数の外国語が操る語学力を得た。ハンガリーと険悪になったポーランドは、まだ10歳であったヤドヴィカを王に指名することになり、ヤドヴィカの人生は大きく変わることになる。
ヤドヴィカは隣国のリトアニアの君主と25歳差で結婚して、中世ポーランドの最盛期を築いた。しかし、厳格なキリスト教徒であったヤドヴィカは質素な生活を好んで満足な食事を取っていなかった。難産によって衰弱したヤドヴィカは26歳で亡くなってしまった。
ンジンガ『奴隷貿易と戦ったアフリカの女王』

(1582〜1663)
アンゴラに実在したンドンゴ王国の女王。黒人奴隷を求めるポルトガルに苦しめされていたンドンゴ王国は、ポルトガルと戦争することを誓った。
兄であるムバンディは一族伝統的な原始的な戦いでポルトガルに挑もうした。銃による戦闘が主流であるヨーロッパに勝てるはずがないとわかっていたンジンガは止めようとするが、上手くは行かない。
むしろ兄に逆らったとンジンガは残酷な体罰を受けた。ンジンガの予想通りンドンゴ王国はポルトガルに惨敗する。和平交渉の話が進みポルトガル語がわかるンジンガが外交官を務めるようになると、彼女の能力は評価されるようになり兄が亡くなった後に即位することになった。
女王となったンジンガは黒人奴隷をヨーロッパに売るなどして、なりふりかまわずポルトガルと戦うことを決断したのだった。ついにはポルトガルと対等な条約を結ぶに至った。
ラナヴァロナ1世『近代化を阻止したマダカスカルの女王』

(1792〜1861)
マダスカルのメリナ王国の女王。メリナ王国の貴族の娘として生まれたラナヴァロナは、王国の妃となった。王であるラダマ1世はヨーロッパの文化を取り込んで、マダカスカル島内での王国の地位を底上げるすることを夢見た。
ラダマが病死すると、権力を欲したラナヴァロナがクーデターを起こして即位した。即位したラナヴァロナは夫であったラダマとは違い、西洋文化を全否定して旧体制に王国を戻そうとした。
しかし、前王同様にマダカスカルでの領土拡大はしたい。ラナヴァロナは隣国に攻撃を仕掛けるが、その隣国がフランスに保護を求めたことで、ヨーロッパの大国と戦うことになる。
ラナヴァロナはヨーロッパと戦うことを決意して、マダカスカル島内のキリスト宣教師を弾圧、追放することを強制した。あまりに強引だったのでイギリスとフランス連合と戦争を起こる。
ついにはキリスト教徒であった息子が所属していた組織によって命を狙われるようになる。息子に裏切られたことはショックだったが、例外として息子を含めた若者は処刑しないことにした。ラナヴァロナの死後に後継者に指名された息子は、国の近代化を進めてマダカスカルはヨーロッパに侵食されていった。